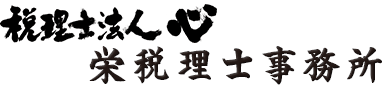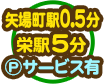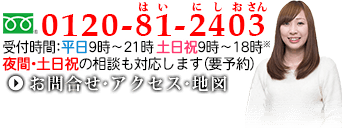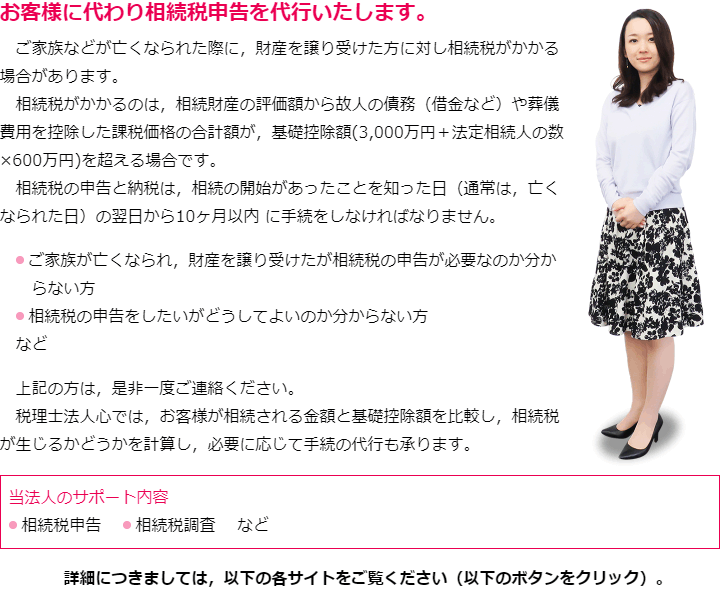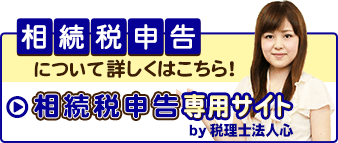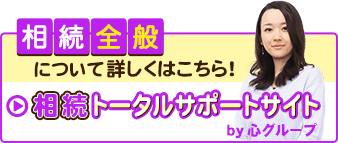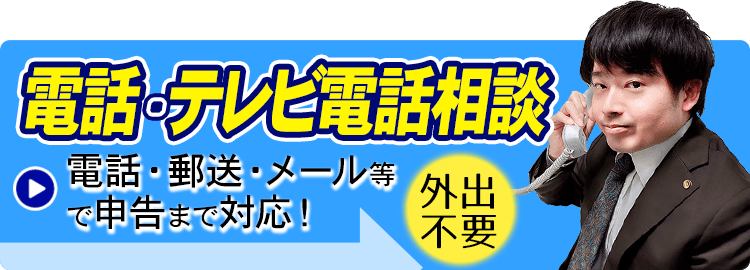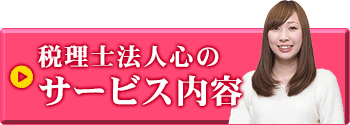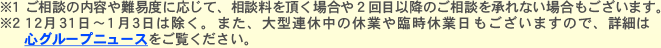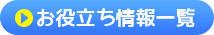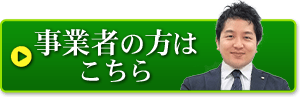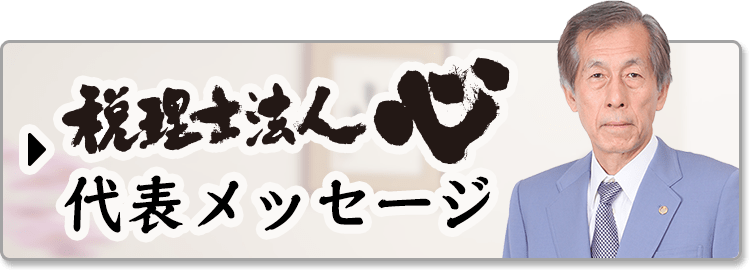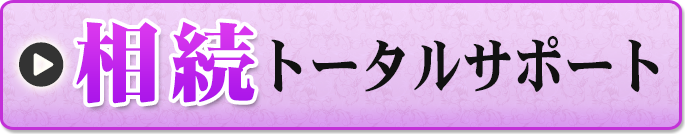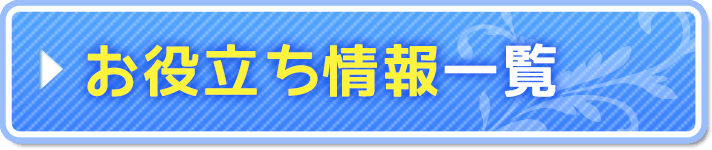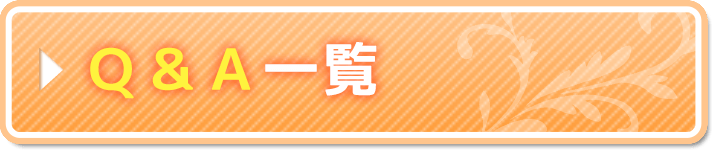相続税申告(相続発生後)
相続税を申告する流れ
1 遺言書の有無を確認する

相続人の間で遺産分割の協議を行ったあとで遺言書が見つかると遺産分割協議をやり直す必要がありますので、先に遺言書の有無を確認します。
公正証書遺言の場合は、公証役場で確認することができます。
自筆証書遺言の場合は、法務局に預けていれば、法務局で確認することができます。
なお、自筆証書遺言は、自宅や銀行の貸金庫等にも保管されてある可能性があることには注意が必要です。
2 相続財産を確認する
亡くなったときの現金、預貯金、不動産、株式等の有価証券、生命保険、お仕事をまだされていた場合は死亡退職金の有無等を確認する必要があります。
預貯金は、ゆうちょ銀行の場合はお近くのゆうちょ銀行に行き、確認を依頼してもらいます。
また、一部の金融機関のなかには、お近くの支店に申し込むと預貯金口座の有無について全店照会をかけてくれるところもあります。
ただ、金融機関によっては、亡くなった方が口座を開設していた支店まで行かなければ口座の有無や残高が確認できないこともあるので、注意が必要です。
不動産は、亡くなった方がお住まいであった市区町村役場に行き、名寄帳を発行してもらう必要があります。
毎年4月頃に送られてくる固定資産税の課税明細書にも不動産の一覧は載っていますが、こちらは固定資産税がかからない不動産(30万円以下のもの)は掲載されていませんので、相続財産が漏れる可能性があることには注意が必要です。
株式等の有価証券は、証券会社か、証券保管振替機構に確認します。
生命保険は、生命保険会社か、一般社団法人生命保険協会に確認します。
3 相続人の有無を確認する
亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの間のすべての戸籍謄本を取り寄せます。
亡くなった時の除籍謄本は、亡くなった際の市区町村役場で取り寄せができますが、結婚時、出生時は別の方の戸籍に入っていますので、順番に戸籍をたどる必要があります。
4 遺産分割協議を行う
相続人が複数おり、遺言書がない場合は、遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するか決め、遺産分割協議書を作成します。
5 相続税申告書を作成する
遺産分割協議書の内容を反映した相続税申告書を作成し、完成すると、申告・納税を行います。
これらの手続を、死亡の日の翌日から10か月以内に行う必要があります。
相続税についての税理士の選び方
1 すべての税理士が相続税に詳しいわけではない

すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。
というのも、税理士の業務分野としては、相続税のほかに、法人税や所得税など多岐にわたります。
そして、税理士はすべての業務分野をまんべんなく取り扱っているわけではありませんし、実は、税理士の主要な業務分野は法人税や所得税です。
税理士試験においても、税務のすべての分野の受験義務があるわけではなく、すべての税理士が相続税の勉強をしているわけでもありません。
そのため、すべての税理士が相続税に詳しいというわけではなく、税理士の中には、そもそも相続税は取り扱っていないという税理士や、1年に1度も取り扱っていないという事務所もあります。
そのような税理士ですと、相続税に関する知識や経験が不足してしまっているため、相続税の申告内容を誤ってしまうおそれがないとはいえません。
相続税に関する知識・経験の少ない税理士に依頼してしまうと、例えば相続財産の調査が不十分であったり、財産評価が不適切であったために税務調査が入ってしまう、適切に特例を適用すれば相続税額を抑えることができたのに多くの税金を払ってしまうなど、依頼される側が、結果的に不利益を被ってしまうおそれがあります。
さらに、相続税に対する生前の対策をしようという場合には、昨今の法改正の内容だけでなく、相続税対策の実務内容についての知見も必要になるため、相談者の方にとって的確なアドバイスを受けられないかもしれません。
そのようなことのないように、相続税については、相続税に詳しい税理士を選んで、依頼をしましょう。
2 どのようにして相続税に詳しい税理士を選べばいいか
⑴ 税理士に依頼する際の注意点
相続税について税理士を選ぶ際は、普段の業務分野が相続税だという税理士を選ぶべきです。
そのため、相続税の依頼では、知人であるというだけで税理士を選んでしまうことや、普段は個人や会社の申告業務をお願いしている税理士に依頼をするということは、できれば避けていただいた方がよいといえます。
もしそのような税理士に依頼をしようと考えた場合には、依頼する前に、普段からどの程度の相続税の案件を取り扱っているかを確認していただくことをお勧めします。
もし普段は相続税の案件を取り扱っていないという場合には、相続税に詳しい税理士に依頼することを検討した方がよいでしょう。
⑵ 相続税に詳しい税理士の探し方
相続税に詳しい税理士に心当たりがない場合には、自ら探す必要があります。
探し方としては、まずは事務所のホームページを確認していただくのがよいと思います。
ホームページを確認して、相続税にどの程度の力を入れているのか、取扱いの実績はどの程度あるのかを見ていただきたいと思います。
また、事務所の場所ですが、相続税に関する相談の際には、事務所で税理士と打ち合わせをしたり、何回かに分けて資料を持っていったりすることもありますので、基本的に、ご相談に訪れやすい場所にある事務所を選ぶべきだといえます。
ただし、電話などでの相談に応じられないわけでもありませんし、遺産の不動産がある場所に近い事務所であることが必須というわけでもありません。
また、相続税に関する疑問や不安について、適切に回答してくれるかどうかを、実際に相談してみて判断するということも効果的です。
まずは、相談の予約を取っていただき、ご相談の中で、税理士がどの程度相続税に詳しいのかをご確認いただいてから、ご依頼をされるのがよいと思います。
相続税申告が必要な場合
1 相続税申告が必要なのはどのような場合か

大切な親族が亡くなられ、悲しみに暮れる中で、役所への届け出や葬儀等、やらなければならないことも多く、戸惑う方も多いと思いますが、相続税の申告も忘れてはなりません。
しかも、相続税の申告は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に行わなければならず、時間制限もあります。
しかし、そもそも相続税の申告をする必要があるのかわからないという方もいらっしゃるでしょう。
そこで、相続税の申告が必要な場合について解説していきます。
2 基礎控除額を超える相続財産がある場合に申告が必要
相続税は、相続する財産の合計額が基礎控除額を超えている場合に、申告する必要があります。
⑴ 基礎控除額とは
基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」という計算式から導かれます。
具体的にいえば、相続人が配偶者と子供二人の場合には、基礎控除額は3000万円+600万円×3人=4800万円となります。
そして、相続財産がその金額を下回る場合には相続税を支払う必要はなく、相続税の申告も必要ないということになります。
⑵ 法定相続人とは
ア 法定相続人の順位
法定相続人とは、民法上相続人となる方のことをいいます。
配偶者は必ず相続人になります。
その他は具体的にいうと、第1順位の相続人として被相続人の子供(子供がすでに他界している場合には孫)、子供がいない(あるいはすでに他界していて、かつ孫もいない)場合には第2順位として被相続人の両親(両親がすでに他界しているが祖父母がご存命の場合は、祖父母)、両親及び祖父母がすでに他界している場合には第3順位として被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹がすでに他界している場合には甥、姪)が法定相続人となります。
イ 養子がいる場合の取り扱い
被相続人に養子がいる場合、養子も第1順位の相続人となります。
ただし、基礎控除額の計算において、法定相続人に含めてもよい養子の数には制限があります。
被相続人に実の子供がいる場合、基礎控除額の計算において法定相続人に含めてもよい養子の数は1人までとされています。
被相続人に実の子供がいない場合、基礎控除額の計算において法定相続人に含めてもよい養子の数は2人までとされています。
これは、多数の養子をとって基礎控除額を増やし、相続税の支払いを免れることができないようにする趣旨で設けられた制限です。
3 相続税の申告が必要か否かの判断に迷ったら税理士にご相談を
相続税の申告が必要か否かは、上述の基礎控除額がいくらか、相続財産がそれを超える額かどうかで判断されます。
しかし、被相続人に養子がいたり、相続人の中にすでに亡くなっている方がいたりするような複雑な場合等には、誰が法定相続人に該当するかの判断に迷う場合もあると思います。
また、他の相続人になる方との関係性が疎遠で、現在も生存しているかわからないような場合には、戸籍等を取り寄せてみなければ法定相続人の数が確定しないという場合もあり得ます。
さらに、基礎控除額を把握できたとしても、相続財産がいくらなのか(基礎控除額を超えるか)については、どれが相続財産に含まれるのか、そして個々の財産の価値をどのように評価したらよいかによって結論が変わりますので、相続税に関する専門的な知識がなければ正しい判断をすることが難しい場合も少なくありません。
しかも、上述のように相続税の申告には期限があるため、期限内に申告をしなければならないかを適切に判断して、もし申告が必要な場合には相続税申告書を作成し、必要資料を揃えて税務署へ提出する必要があります。
専門的な知識がないまま相続税申告をしなかったり、間違った内容で申告してしまうと、延滞税や無申告加算税、過少申告加算税などのペナルティが課される可能性もあるため、相続税の申告をする必要があるかどうかは、税理士に判断を仰いだ方がよいです。
「相続税の申告が必要かどうかわからない」「申告をしなくてよいのか不安だ」といったことでお悩みの方は、税理士法人心までお気軽にご相談ください。
相続税の申告をするための準備
1 相続税の申告期限の確認

相続税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告をしなければなりません。
相続税の申告をするためには、さまざまな準備が必要です。
万一、相続税の申告が間に合わなかった場合には、申告期限に遅れたことによるペナルティを受けることになります。
この場合には、申告が遅れたことによる税金の加算があったり、利用できたはずの特例が利用できなくなったりということがありますので、事前に期限をしっかりと確認した上で準備を進めましょう。
2 相続人を確定させる作業
相続税の申告をするためには、相続人を確定する作業が必要です。
⑴ 相続人の調べ方
相続人を確定させるには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が必要です。
また、相続人全員の現在の戸籍も必要になります。
代襲相続が発生していた場合(たとえば、亡くなった方の子どもが、すでに亡くなっており、孫が相続人となる場合など)には、被代襲者(先に亡くなっていた子)の出生から死亡までの戸籍も必要になります。
相続人は法律で順位が定められており、誰が相続人になるのかはこれで決まりますし、それに対応して、どの範囲で戸籍が必要になるかが決まってくるのです。
⑵ 相続人を調べる意味
相続税には、基礎控除額というものがあり、相続財産総額が基礎控除額を下回っている場合には相続税を支払う必要がなく、相続財産総額が基礎控除額を上回っている場合、上回っている部分に対してのみ相続税が課されます。
相続税の基礎控除額は、「3000万円+相続人の数×600万円」という計算式によって導かれますので、相続人の人数を確定して初めて基礎控除額が変わってきます。
詳細は税理士にご相談ください。
3 相続財産の有無の調査
相続税の申告をするためには、相続財産を調査する作業が必要です。
相続財産を調査する方法は、不動産や預貯金など財産の種類によって異なります。
⑴ 不動産
不動産については、自宅に届いている固定資産税等の納税通知書などを調べることで把握することができますし、これが見つからない場合には、市町村役場で名寄帳や固定資産税評価証明書を取得することで、不動産を把握することができます。
これをもとにして法務局にて不動産の登記簿を取得した場合に、抵当権の共同担保がついていれば、これによって他の不動産があることを把握することもできるでしょう。
⑵ 預貯金
預貯金については、自宅内で通帳を探すことが有効です。
通帳が見つかった場合には、その取引の内容を確認することも重要です。
取引の内容の中に、保険料などの引落しがあれば、生命保険に加入していた可能性があります。
また、取引の内容の中に、「キンコリョウ」などの記載があれば、その金融機関に貸金庫があった可能性がありますので、貸金庫の中を調べた結果、相続財産が新たに判明することもあるでしょう。
そのほかにも、たとえば、年金を受給していたはずなのに、年金を受け取っていた口座が見つからない場合には、判明していない口座がある可能性があります。
判明している口座以外に預貯金があると予想できる場合には、追加の調査が必要です。
相続人の立場であれば、金融機関に口座の有無を照会できますので、亡くなった方が口座を持っていそうな金融機関(たとえば、亡くなった方のご自宅近くに支店のある銀行・信用金庫等)に照会をして調査をしましょう。
⑶ その他
その他の財産として、株式や保険などがありますが、それぞれについての調査の方法があります。
4 相続財産の資料の収集
相続税の申告にあたっては、相続の開始時点での相続財産の内容を明らかにする必要がありますので、これのもととなる資料を準備する必要があります。
不動産を例にとって説明すると、必要資料としては面積や住所、持ち分を明らかにするための登記簿、土地の形や近隣の状況を把握するための公図などが必要になります。
そして、これらの資料をもとに、たとえば土地は、路線価方式や倍率方式などで算出された評価額に、土地の形状や広さなどによる必要な補正を加えたうえで、その評価額が決まります。
要件を満たせば、小規模宅地等の特例を利用することで、評価額を下げることもできます。
このように、相続財産が相続の開始時においていくらの価値があったのかが分かるために必要な書類をそれぞれの財産に応じて準備していく必要があります。
5 納税資金の準備
通常は、相続税の申告と同時に納付も行います。
期限までに納税資金を準備しましょう。
場合によっては、相続税の額は非常に高額になりますし、相続財産を納税資金に充てようと考えていたとしても、このときまでに遺産分割協議が成立していないなどの事情があった場合には、相続人自身の資金から相続税を納付しなければならないこともあります。
相続財産の大部分が不動産であった場合などには、不動産を売却するなどしなければ相続税を支払えないという場合もありえます。
相続財産の調査を進めながら、納税額がいくらになりそうかの概算をしておくことで、納税についての計画を立てることができます。
6 準備はなるべく早く進める
このように相続税の申告のためにはさまざまな準備が必要です。
申告や納税の期限に遅れないように、なるべく早く準備を進めることが必要です。
どのような準備を進めればよいのかは、税理士のサポートを受けずに進めることは難しいと思いますので、そのアドバイスを受けながら着実に相続税の準備をするようにしてください。
どのような財産が相続税の対象となるのか
1 相続税について知りたいという方へ

このページをご覧になられている方の中には、大切なご親族が亡くなられて相続税の申告をしなければならないという方、あるいはご親族に不幸があった場合に備えてあらかじめ相続税の知識を得ておきたいという方もいらっしゃるかもしれません。
そのような方へ向けて、そもそもどのような財産が相続税の対象となるのかについて解説していきます。
2 不動産
まず、大きな財産として、土地や建物などの不動産が挙げられます。
不動産を漏れなく申告するためには、名寄帳を取り寄せることが有効です。
なお、建物については、固定資産税評価額通りの金額で財産価値を評価することになりますが、土地については複雑な評価が必要になる場合もありますので、注意が必要です。
3 現金、預貯金
亡くなった方が死亡した時点で持っていた手持ち現金やタンス預金、銀行に預けていた預金なども相続財産となります。
また、例えば銀行の名義は亡くなった方の配偶者や子、孫だったとしても、実質的には亡くなった方の財産と評価される場合(いわゆる「名義預金」に該当する場合)には、それも相続財産に含めなければなりません。
4 有価証券
株、国債などの有価証券も相続財産に含まれます。
上場株式については、証券会社から株の銘柄や持株数等を開示してもらい、適切に評価をする必要があります。
5 その他の財産
誰かにお金を貸していた場合の貸付金や、貴金属、特許権、著作権等も相続財産に含まれます。
また、亡くなる直前に相続人や受遺者に対して生前贈与された金額も、相続財産に含めなければならないこととなっています。
具体的には、令和5年までに贈与されたものについては、相続開始の直近3年間に贈与された金額が相続財産に含まれます。
また、令和6年以降に贈与された金額については、直近7年間に贈与された金額が相続財産に含まれます。
ただし、この規定には経過措置が設けられており、令和12年中までに発生した相続については、令和6年1月1日以降に贈与された金額が相続財産に含まれることになります。
したがって、例えば、令和6年6月1日の相続に場合は、令和3年6月1日以降に贈与された金額が相続財産に含まれ、令和10年1月1日の相続の場合には、令和6年1月1日以降に贈与された金額が相続財産に含まれます。
6 みなし相続財産
相続税の対象となるものとして、みなし相続財産と呼ばれるものがあります。
典型例は、故人が亡くなった際に支払われる死亡保険金や死亡退職金です。
これらは、故人が亡くなったことを原因として発生するものであって、故人が亡くなった時点で所持していた財産ではありませんが、相続財産とみなされます。
ただし、いずれについても「500万円×法定相続人の数」に相当する金額までは、相続税がかからないことになっています。
7 相続税のご相談は税理士法人心まで
相続税の申告には、相続財産に該当する財産を漏れなく把握し、適切にその価値を評価することが必要となります。
しかし、相続税の申告及び納税は、故人が亡くなってから10か月以内に完了しなければならず、時間も限られています。
ご自身で相続税の申告をすることに不安のある方は、税理士法人心までお気軽にご相談ください。
相続税の申告に関する書類
1 相続税の申告に必要な書類は何か

被相続人が亡くなって相続が発生した場合、相続財産の金額によっては相続税の申告及び納税をしなければなりません。
そして、相続税の申告に当たっては、税務署に対して様々な資料を提出しなければなりません。
では、どのような資料を提出しなければならないのでしょうか。
2 相続人・被相続人に関する書類
相続税は、「3000万円+法定相続人の数×600万円」から算出される基礎控除額を超える場合に納付が必要になりますから、法定相続人を調べる必要がります。
そこで、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本、相続人の戸籍謄本及び住民票などが必要です。
また、相続税の申告は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に対して行わなければならないため、最後の住所地を調べるために被相続人の戸籍の附票または住民票の除票も必要となります。
3 遺産分割に関する書類
被相続人が遺言書を残している場合には遺言書、遺言書がなく相続人同士で遺産分割の協議をした場合には遺産分割協議書の提出が必要です。
これは、誰がどれくらいの財産を受け取るかによって、各相続人の負担すべき相続税の金額が変わってくるため、提出が必要になります。
また、もし遺産分割がまとまっていない場合には、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例等の相続税負担を軽減する特例が使えませんので、分割方法がまとまっているかを確認する必要があるため、提出が必要になります。
なお、もし相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらなかった場合、とりあえず法定相続分で分割したと仮定して、配偶者の税額軽減等の特例を適用がない前提で申告・納税を行い、その際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することになります。
このようにすれば、後日遺産分割協議がまとまった後に、その協議内容に従って修正申告をすれば、その際には配偶者の税額軽減等の特例を適用できますので、一旦収めた税金の返還を受けることができます。
4 相続財産に関する書類
⑴ 不動産
相続財産に不動産が含まれる場合には、その不動産の登記簿謄本、固定資産税評価証明書が必要になります。
また、土地については、所在地によっては土地の形状や周辺の状況など様々な要素を考慮してその価値を評価しなければならないため、公図又は測量図、住宅地図なども必要となります。
もっとも、固定資産税評価証明書以外の書類は、相続税申告に慣れた税理士であれば、代わりに取り寄せることも可能です。
⑵ 預貯金
預貯金については、銀行から亡くなった日時点での残高証明書を出してもらい、それを提出する必要があります。
⑶ 有価証券
株などの有価証券については、証券会社に残高証明書を出してもらい、それを提出する必要があります。
⑷ 生命保険
被相続人が亡くなったことによって死亡保険金が支払われた場合、生命保険会社から発行される保険金の支払通知書、保険金の受取人が分かるような保険証券の写しなどが必要になります。
⑸ 退職金
被相続人が亡くなったことで死亡退職金が支払われた場合、会社から発行される退職金支払通知書が必要になります。
⑹ 解約返戻金
被相続人の加入していた保険のうち、解約返戻金がある場合、保険会社に亡くなった日時点での解約返戻金額証明書を発行してもらう必要があります。
⑺ 自動車
被相続人が自動車を所有していた場合には、車検証のコピーを提出する必要があります。
5 相続財産から差し引くものに関する資料
⑴ 債務
生前に被相続人が支払うべきだった借金、水道光熱費、医療費などの債務がある場合、その請求書や、相続人が支払った場合にはその領収証等の写しがあれば、相続財産から差し引くことが可能です。
⑵ 葬儀費用
被相続人の葬儀のために支払った費用については、その領収証や葬儀会社から出された請求書などがあれば、相続財産から差し引くことが可能です。
なお、葬儀費用の中でも、一部差し引くことができないものもありますので、葬儀会社に葬儀代を支払った際の領収証ではなく、葬儀代の内訳が分かる書類が必要になります。
6 相続税に関するご相談は当法人まで
ここまで、相続税申告に必要な資料の代表的なものをご説明しました。
相続財産の内容によってはその他にも必要となる資料がありますので、詳しくは当法人までご相談ください。
相続税に関する代表的な特例
1 相続税に関する特例

相続税とは、亡くなった方の財産を相続した際に納めなければならない税金のことをいいます。
もっとも、相続した財産は残されたご家族の今後の生活の糧になるものですから、相続税は極力安く抑えたいところだと思います。
そこで、相続税を安く抑えるための特例の代表的なものについて、見ていきましょう。
2 基礎控除
どなたでも使うことができる特例として、基礎控除というものがあります。
相続財産総額から基礎控除額を引いた金額に対して相続税が課されることになります。
また、相続財産総額が、基礎控除額を下回る場合には、相続税を支払う必要はなく、相続税の申告すら必要ありません。
なお、基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」によって算出されます。
3 小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例は、被相続人が住んでいた家の敷地や、事業用建物の敷地などについて、要件を満たせば50~80%その評価額を減らすことができます。
土地は、相続財産の中でも最も大きな価値を占めることが多い財産ですので、その価値を大幅に減額することができれば、相続税額を減らすことができますので、適用できる土地がないか、忘れずに検討しましょう。
4 相続税を減額する特例
⑴ 配偶者控除
被相続人の配偶者については、法定相続分または1億6千万円までは、相続税が免除されます。
⑵ 未成年者控除
相続人のうち未成年者については、「18歳(令和4年3月31日以前の相続または遺贈については20歳)に達するまでの年数×10万円」の相続税控除を受けることができます。
⑶ 障害者控除
障害者が相続人となる場合、「85歳に達するまでの年数×10万円(特別障害者に当たる場合には20万円)」の相続税控除を受けることができます。
⑷ 相次相続控除
10年以内に2回以上の相続が発生した場合、1回目の相続の際に課せられた税額の一定割合に当たる金額が、2回目の相続税の金額から控除されます。
⑸ 贈与税額控除
被相続人が亡くなってから3年以内に贈与された金額は、相続財産に含めなければなりませんが(※)、その贈与の際に支払った贈与税額分、相続税から控除されます。
※ 令和5年の税制改正により、令和6年1月1日以降の贈与については、被相続人が亡くなった時の直近7年以内のものについて、相続財産に含めなければならなくなりましたが、延長された4年間については、100万円までは加算されません。
5 相続税が非課税となるもの
⑴ 生命保険金
被相続人が亡くなったことにより相続人が受け取った生命保険金は、相続財産とみなされます。
ただし、そのうち、「500万円×法定相続人の数」分の金額は、相続税が課されません。
⑵ 死亡退職金
被相続人が亡くなったことで、退職金等が相続人に支払われた場合、その金額は相続財産とみなされます。
ただし、そのうち「500万円×法定相続人の数」分の金額は、相続税が課されません。
6 相続税のご相談は税理士法人心まで
以上、相続税申告の際に利用できる特例のうち、代表的なものをご紹介しました。
これらの特例のうち、どれが適用できるのか、適用するとどれくらいの相続税がかかるのかについて詳しく知りたいという方は、税理士法人心までご相談ください。
相続税を適切に申告・納付しないとどうなるのか
1 相続税の申告期限

相続が発生した場合、相続財産の金額に応じて相続税の申告・納付をしなければなりません。
相続税の申告・納付期限は、「被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内」です。
例えば、4月15日に亡くなりそれを知った場合、翌年の2月15日が相続税の申告・納付期限となります。
なお、相続税の申告・納付期限が土日祝日であった場合、その次の平日が期限となります。
2 期限内に申告・納付しないとどうなるのか
期限内に申告・納付をしなかった場合、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課されます。
⑴ 無申告加算税
無申告加算税は、期限内に申告・納付をしなかったこと自体に対するペナルティです。
無申告加算税は、①税務調査の事前通知を受けるまでに自主的に申告・納付をした場合には5%、②税務調査の事前通知を受け、税務調査を受ける前に自主的に申告・納付をした場合には10~25%、③税務調査を受けてから申告した場合には15~30%の税率で課されます。
なお、期限を過ぎた場合でも、申告期限から1か月以内に自主的に申告を行い、かつ、期限内に申告をする意思があったということが認められるような一定の場合に当てはまるケースについては、無申告加算税が免除されることもあります。
⑵ 延滞税
延滞税は、申告・納付期限から、実際に申告・納付をするまでの日数に応じてかかるペナルティです。
延滞税は、期限から2か月以内であれば「年7.3%」又は「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い方、2か月を経過した後であれば「年14.6%」又は「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い方となりますが、延滞税率は毎年変動しますので、その都度確認する必要があります。
参考リンク:国税庁・延滞税の割合
3 申告・納付に誤りがあった場合はどうなるのか
⑴ 相続税を多く申告・納付してしまった場合
相続税を申告したものの、本来申告・納付すべき金額よりも多く申告してしまい、相続税を払い過ぎてしまったという場合には、特段ペナルティはありません。
もっとも、相続税を払い過ぎたからといって、税務署からその旨の連絡が来ることはありませんので、払い過ぎに気づかずに損をしてしまう方が多いです。
後で払い過ぎに気づき、払い過ぎた分を取り戻そうとする場合、更正の請求をすることが可能ですが、一旦納付された相続税の返金を求める手続きであることから、税務署は厳しく判断をしてくることが多いため、ハードルは高いといえます。
⑵ 相続税を少なく申告・納付してしまった場合
本来支払うべき金額よりも少ない金額で申告・納付してしまった場合、修正申告をする必要があります。
修正申告が必要となった場合、過少申告加算税及び延滞税というペナルティがあります。
もっとも、税務調査の事前通知や、税務調査による指摘を受けるよりも前に、自主的に修正申告を行った場合には、過少申告加算税は課せられませんので、修正の必要がある場合には早めに、自主的に修正申告をするのがよいといえます。
また、延滞税については、本来納付すべき金額とすでに納付した金額との差額の部分について課せられます。
延滞税は、納付が遅れた日数に応じて課せられるので、この点でも修正申告をする必要がある場合には、早めの対応をすることが大事です。
4 相続税の申告に関するご相談は税理士法人心まで
このように、相続税の申告・納付を正しく行わないと様々なペナルティが課せられますので、期限内に正しく申告をする必要があります。
もっとも、相続税申告を適切に行うためには、10か月という限られた期間内に、相続財産を漏れなく把握し、その財産の価値を適切に評価した上で、場合によっては、適用できる特例等を使って相続税を減額できるかを検討するなどして、過不足なく申告・納税をする必要があります。
しかし、相続税申告に慣れていない方にとっては、なかなかハードルが高い作業といえますので、期限内に適切に申告・納付をすることができるか不安に思われる方は、信頼できる税理士に任せた方がよいでしょう。
相続税に関するご相談は、税理士法人心までお気軽にお問い合わせください。